

この世界で起こることすべては、いずれ科学で説明がつき、技術で再現することができる、という考え方があります。
もしそれが本当だとしても、実現できるのは遠い将来のこと。
おそらく科学や技術が進歩するほど、世界の謎は深まるばかりという方が、ありそうな未来です。
すでに科学技術によって解決済みとされているテーマにしても、よくよく見直してみれば、落としものや忘れものだらけ。
しかもそれらは、いちばん大切で、しかも日々の生活のすぐそばにあったりするようです。
たとえば、勘や気配や予感をはじめ、合理的に説明されたように思えても、どこか腑に落ちないものは、決して少なくありません。
思えば現代文明はずいぶんたくさんの忘れものをしてきてしまいました。
しばしの間、立ち止まって、あれこれ思い出してみるときが来ているのかもしれません。
来るべき科学や技術の種は、そんな忘れものの中で、見つけられるのを、いまや遅しと待っているのです。
堀場製作所
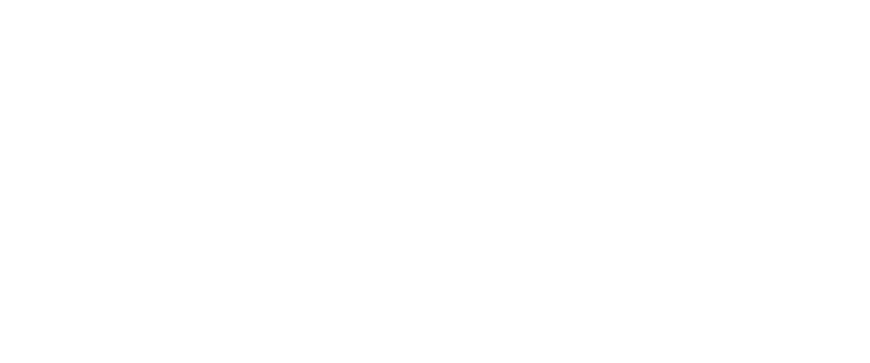

◉現代では職人といえば、主に手工業に携わる人々を指しますが、もともとは特殊な技能を持っている者のことでした。古代では鉄器鍛冶や庭師がその代表です。中世になると貨幣経済と物流が発展したことと相まって、多様な職人たちが登場します。そして近世までの「職人」は、単にモノを生産する人を意味したわけではありません。連歌師や白拍子、勧進聖や神主などコトにかかわる者、つまり芸能者や宗教者たちも、職人と呼ばれていました。市や街道は、そんな職人たちによるモノやコトが交換される場所だったのです。
◉才能という言葉があります。才と能は別の意味を持ちつつ、切り離すことができません。かつて才は「ざえ」と読み、人間の側ではなく素材の側に備わっているものとされていました。木や石、場合によっては風景や気象の才に感応し、これを引き出す人間の力が能であり、それはマジカルな力であるとも考えられていました。漢字の「職」が耳につけられた呪術的なしるしをあらわしているように、職人とは、常人には聞くことのできない自然や神仏の声を聞く能力を持つ人々だったのです。もちろんここで言う「聞く」は音響だけに対応するわけではありません。
◉中世には職人を題材とした「職人歌合」が流行しました。歌合は歌の優劣を競う遊びですが、職人歌合は、朝廷や貴族に従属する職人を描写することによって、怨霊や祟りを鎮めることが目的とされていたといいます。江戸時代には、三味線の名手の原武太夫が、弦の音色がいつもと違っているのを聞き、津波を予見して仲間の命を救ったというエピソードも残されています。
◉レンズや金属加工の領域でミクロン単位の対象の変化を触知するというような単純な物理量をめぐる感覚は、確かに超絶的ではありますが、テクノロジーによって置き換えることが可能となりつつあります。しかし琴の音色で、それがナイロン弦なのか絹糸製であるのかはもちろん、絹糸をつくった蚕の飼育方法や飼料の変化を聞き分けたり、墨の匂いで古文書の書写年代を嗅ぎ当てたりといったことは、コンピュータでは代替できそうにはありません。また、調香師になるためには最低600以上の匂いを正確に記憶しなくてはなりません。それ自体は物質分析の領域ですが、調香師の本領はそこから先、つまり未知の香料や香水をつくり出すことにあり、ときには好き嫌いのような感覚にも深くかかわる以上、テクノロジーでは単純には代替できません。そもそも人間の感覚は気分や体調によって大きく左右され、そのこと自体が例外的な感覚に結びついていたりもします。少なくともいまのところ、スーパーコンピュータを駆使した天気予報でさえ、経験豊富な漁師たちの感覚や勘には、まだまだ及びもつかないようです。

◉人間は成長にしたがって感覚が発達し、肉体の成熟とともに感覚の能力もピークに達するといいます。その後は経験とトレーニングによって感覚は磨かれますが、基本的な能力は減衰する一方です。確かに言語をめぐる感覚や、渋味や苦味などを味わう感覚は、成人の方が豊かであるようにも見えます。しかし絶対音感は生来のもの、あるいは幼児期に獲得できるものであり、外国語の習得もスタートが早い方が有利であるともされています。ちなみに絶対音感は、必ずしも「絶対的」な音感ではなく、また環境音まで西洋音楽の十二平均律に「翻訳」してしまう傾向があるなど、一概に音楽的に優れた能力であるとは言えないようです。また母語習得前に外国語を学ぶことへの弊害も指摘されています。
◉我々は、たとえば日本人ならば同じアジア人であっても、インドの人々の顔だちは皆、同じように見えてしまいます。逆にインド人にとっては、日本人の顔は似たり寄ったりに見えているはずです。最近では多くのメディアによって欧米人の顔に馴染んでいるため、欧米の俳優や政治家の顔の区別はできるようになっていますが、江戸時代の日本人にとっては、白人は一様に、赤ら顔の鼻の極端に尖った人たちに見えていました。また動物園の猿山のニホンザルをその顔で区別できる人は、当の飼育員でない限りほとんどいないと言っていいでしょう。かろうじて毛色や大きさや傷の有無などで判別できるくらいです。ところが多くの幼児は、この猿山の猿たちの顔を見分けることができます。この例では、成長にしたがって、すなわち人間社会に馴染み、言葉によるコミュニケーションに習熟するにしたがって、猿の個性が見分けられなくなっていくわけです。どうやら我々の一般的な感覚は、本来の能力にフィルターをかけることによって成立しているようです。いちばんのフィルターは、言葉です。職人たちの超絶的な感覚は、収斂によって研ぎすまされるのと同時に、このフィルターをあらためて剥ぎ取ることで獲得されているのかもしれません。
◉確かに言葉は、脳に保存されている膨大な感覚の記憶をプログラムし、オペレーションするための有効な道具でした。それによって人類は文明を獲得したと言うこともできます。しかし言葉の獲得に続いて文字が発明されると、我々の感覚にはさらに強力な拘束がかかり、同時に感覚の中で視覚が圧倒的な優位に立つことにもなりました。もしかすると絶対音階、あるいは平均律も聴覚への何らかの拘束になっているのかもしれません。犬や猫、鳥や魚などの動物たちがときに地震や天候の変化を予知することができるのに、人間がそれを苦手とするようになってしまったのは、言葉によって生来の感覚に蓋をされてしまったためなのでしょう。方向感覚や時間感覚も、文明や科学技術によって鈍化している可能性があります。