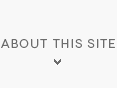科学的なロジックと
物語的なロジック
人間も動物も、そして植物も、生きることは、表現し続けるということではないでしょうか。表現をやめるのは、死ぬこととほとんど同じ。生命の働きがそれぞれに異なっていながら、地球という規模ではまとまっているのは、表現が相互に整合しているからです。
植物では、多様な樹木が種を超えてコミュニケーションし合い、自然林を形づくっています。人工林ではそういうことがうまくできていませんが、自然林ではいくつかのグループを構成しつつ、それが崩れたり結びついたりして、持続している。以前は、このような持続、つながりということを頭で考えていましたが、自らそこに入り込み何かを表現することで見えてくるものがある。主観と客観を分けない世界をどうつくるか、ということにも関係します。科学と宗教という分け方においても、それを統合しようとすると、「大きな生命の働き」というようなことが語られる。しかし具体的には、表現をつくり合うということが重要な視点になります。背景の違う人たちがともに表現をつくり合っていくのが、共創ということなのでしょう。深い部分でのつながりの解明は、生命の働きとは何かという問いに答えることと不可分ですが、一方には科学的なロジックがあり、他方には生きる、すなわち人生のドラマをつくっていくという物語的なロジックがある。現在はこの両者が分離しています。
ドゥーイングと
ビーイングの
ミスマッチ
リハビリなどの現場では、介助する側とされる側の間で、コミュニケーションがうまくいかないケースをよく眼にします。介助する方にとっては、機能的に腕が上がることが目標とされる。しかし介助される側は多くの場合、自分が完全には戻らないことを知っている。でも戻りたい。本当は、戻れない自分が今後どう生きていくのかということに気づかないといけない。その気づきを起こすことこそをサポートすべきだし、それでなくてはコミュニケーションもうまくいきません。一方はどう生きるかが問題なのに、片方は何をすべきかを目的にしている。ドゥーイングとビーイングのミスマッチがあると、エラーが起こります。どう生きたいのかということを共有した上で、いま何をすべきかということに向き合うという、二重構造的なコミュニケーションが必要なのです。
この「どうすべきか」のところだけをやっているのが、現在の携帯電話やITのコミュニケーション・ツールです。だから機能的なシステムしかできない。現代の子どもたちの多くは、表現意欲が落ちている。実は、大人もそうなんですが、記号だけで通信するのが常態になっている。微妙なニュアンスが含まれているかもしれないメッセージを、そのまま受けとってしまい、解釈の意味が共有されていないためです。
Column 1
植物のコミュニケーション植物には種によって原型的な生体電位の波形があり、ツバキならツバキのパターン、ミズナラならミズナラのパターンと呼べるような共通したパターンがあるが、山に入ると、その波形が消え、新たにグループ共通の波形がつくり出される。自然林では、多様な種を含むそれぞれ20〜30本くらいからなるグループを形成しており、季節によってメンバーの入れ替えも行われる。一方、一様な樹種から構成される人工林では、基本的に生体電位の波形も一様である。人工林はまた、間伐された樹木を肥料にしている。つまり間伐された樹木を排他していくという競争原理が中心にあり、均一で一様な波形を出していない樹木は、排除されていく。間伐のプロは、そのあたりを無意識のうちに見抜いており、大抵の場合、生体電位がアブノーマルな波形を示すものが伐られているという。
インクルーシブ・
デザインと
インクルーシブ・
ダンス
インクルーシブ・デザインという言葉があります。ユニバーサル・デザイン以降のもので、いわば気づきのデザインです。ユニバーサル・デザインは、高齢者や身障者の人たちの意見を集約し平準化してデザインする。インクルーシブ・デザインは、高齢者や身障者の人たちが設計の現場に入り、最後まで一緒にデザインをする。すると開発者の方が気づかされる。
インクルーシブは日本語では包摂的と訳されますが、障害の有無や年齢にかかわらず、立場を等しくして何かをつくろうというものです。製品をつくることもあるし、作品やパフォーマンスをつくりあげる場合もあります。その中で人と人のつながりがつくられていく。
東洋英和女学院の西洋子先生によるインクルーシブ・ダンスは、たとえばふたりが手のひらを合わせ即興的に体を動かして関係をつくっていく。車椅子の子どもたちがダンスをしている現場を、学生たちと見学したのですが、一緒に入って下さいと言われても、何となく入りにくい。触れていいのか、押していいのか、ためらいがある。何とか一緒になってやっていると、いつの間にか、学生の方が主体性を引き出されている。
インクルーシブ・ダンスは、即興ですからルールはない。その上で少し先の未来が共有されている。それは、場を共有することでもある。場の働きは過去からの延長でとらえるものではなく、少し先の未来を共有することで、現在の表現が合致する。すなわち表現の同時性・総合性・等価性が導かれる。健常者も障害者も、表現においては対等だということです。
西さんの論文には、「包まれつつ包む、包みつつ包まれる」といってよい表現がある。あたかもひとつの大きな身体に包まれているという状態です。完全にひとつになったままだと閉じてしまうので、ときに離れ、ときに合わせる。
「みずから」から
「おのずから」へ
現在、手のひらを合わせ表現をつくり合うことによって互いの気持ちが共有されていくという現象の、ダイナミクスを調べていますが、それができれば、遠隔地同士でつながりをつくることも可能になる。手のひらは掌と書いてたなごころとも言いますが、手の心を伝え合うようなことも考えています。通常、手のひらを合わせて体を動かすと、体の各所がほとんど全部一致して動く。ところがイメージをもって動くと、先行的に動く部分がある。意識して手を動かす前に、無意識に動いているところがある。0.3秒くらいの時間差です。この先行的で無意識的な動きが、手のひらを合わせた同士で時間的に一致する。
「みずから」動いてはいるのですが、それが「おのずから」になっていく。場の共鳴が起こって表現がつくられる。不思議なことに、そのとき1/fゆらぎが出ています。意識と無意識が相互に乗り入れる領域が、非常に重要です。その境界領域に、場が立ち上がる。そこが共振して、相手とつながっている。表現は前へ前へ、未来の方へ進んでいくので、領域はどんどん変化していきます。

◉手のひらを合わせてつながりのダイナミクスを調べる。
余白とメディアの将来
現行メディア、とくにデジタル技術は見えるところしか扱えない。たとえばCGの向こう側はないことにする。これまでのシステムでは、境界条件を与えることではじめて、設計デザインができる。実はその境界条件には客観性はないのですが、理工学系はこれを設定しないと何もできない。外側は無視し、内側の問題としてデザインする。外側が乗り入れるような境界のデザインは、まったくされていない。表現は、自ら境界をつくり続けるということです。境界、拘束条件を自分でつくるのは、生命の基本の働きです。
これまでのメディアは名詞的なメディアと言ってもいい。先に名詞を与える「もの」の世界です。「こと」的に動詞側から動くことで名詞が出てくるメディアがあってもいいと思います。おそらく日本の枯山水や俳句、神社や能は、そういうやり方でつくられている。余白をつくって、そこに主語を浮かび上がらせる。余白は書き残しではなく、何かが生まれる場所なのです。自然とつながっている部分を残している。開かれているわけです。自然、あるいは死の世界を切り離さない。死んだ人も自然も、生きている人もひっくるめての現在です。
「もつためにある」、つまり近代西洋文明の、所有のために拡張拡大するという手法が無効になりつつあります。「あるためにもつ」という方向に転換しなくてはいけないことを、西洋も薄々感じはじめている。産業のための工学という考え方に加え、文化のための工学、社会のための工学という考え方があってもいい。機能のための技術から、存在のための技術へということでもあります。震災後の日本にこそ、この方法を示す可能性があります。存在と機能が循環する技術がいちばんいいのでしょうが、これまであまりにも科学の原理を人間に適用し、人間はかくあるものだと規定しすぎてきたようです。

◉かげを使ったコミュニケーション・システム。
Column 2
かげのメディア三輪研究室では、かげを使ったコミュニケーション・システムを開発している。スクリーン・ルームに入ると、コンピュータによってさまざまなボリュームやかたちに変換された自分のかげが、床や壁面に投影される。他者のかげに自分のかげで触れたり、互いのかげを合成したりしているうちに、言葉を介さない不思議な一体感が生まれる。かつての「影踏み」遊びにも通じるものだ。
かげは鏡と異なり、体とつながっていて完結していないこともあって、一種の余白としてかかわることができるため、身体の中にあるイメージを引き出すためのトリガーとなる。