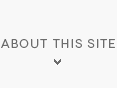「折れぬ、曲らぬ、切れる」を越えて
月山鍛治の伝統
備前の刀剣技術は備前伝、大和は大和伝、相模は相州伝と呼ばれ、中でも相州伝を完成させた鎌倉後期の正宗は、刀剣技術のピークをかたちづくっています。鎌倉室町期は、刀匠が意識して競い合っていた時代でもあります。もちろん江戸時代にも助広、虎徹をはじめとして優れた刀匠がいます。決して正宗に劣っているわけではありません。
現代でも多くの刀匠が正宗をはじめとした名人たちを目指しています。もちろん鋼が経年変化して、うるおいや味わいが増しているのでしょうが、ただ古いからいいというわけではありません。それぞれの時代に名人が出ています。それらの凄さはある程度数を見ないとわからないのかもしれません。悪い刀は、一目見て品格が感じられません。具体的には、反りや姿が悪く、焼きが冴えていないということになりますが、やはり目を養わなくてはわかるものではありません。
月山伝は、その名の通り、奥州出羽月山の流れで、綾杉肌が特徴です。伝承によれば、出羽国月山の霊場に住んだ鬼王丸(鬼神太夫とも呼ばれる)が元祖。以来月山の山麓では刀鍛冶が栄え、多くの名人を輩出しました。鎌倉期から室町期にかけて、月山の銘を刻んだ刀剣はその実用性の高さと綾杉肌の美しさの両面から全国に広まりましたが、戦国時代が終わると月山鍛冶は少なくなります。もともと月山は山岳信仰の拠点で、月山鍛冶はそこに籠って身を浄めて刀を打った特殊な刀鍛冶です。修験者のような行をします。月山というのはご神体の名でもあり、それを刀の銘として刻むのは普通は許されないことです。本来は、武器というより守り刀に類するものだったのかもしれません。月山の刀は人を殺めるものではなく、信仰と結びついていたと私は思います。月山伝の綾杉肌は、ある段階で炭素量の異なる鋼を合わせ、混じり合っていったときの層があらわれたのもので、その加減が秘伝となっていました。
月山鍛冶の後継者として、幕末に月山貞治が大阪に出てきました。もういちど月山を世に問うという気概があったのだと思います。私の曾祖父の初代月山貞一は、たいへんな技術の持ち主であり、鎌倉時代に活動していれば、正宗と比肩しうる人だったと思います。月山伝はもちろん、備前伝、相州伝、大和伝、山城伝、美濃伝などの技法で、いずれも水準以上のものを遺しています。刀剣彫刻もした。そんな人はほかにいません。数百年後には、時代も加わって味わいもいっそう増していくはずです。大阪からここ三輪の地へ移ったのは父、二代貞一の時代。かつて、修験者たちは、月山の刀を腰にさし、大和に来て、大峰山に登り、この三輪を訪れていたのかもしれません。三輪山の中腹に月山谷という地名があるのです。
一心不乱に
鋼を鍛える
日本刀をつくりあげるのは、ほぼ1年がかりの工程で、そのプロセスは複雑です。無事に仕上げるのはなかなか難しいもので、焼物と同じようにすべてが完成に至るわけではありません。3本か4本打って、そのうちの一振りに焼きを入れてひとまずの完成品となる。途中で傷が出たらそこでストップ。また玉鋼(たまはがね)からはじめます。玉鋼は、たたらの製法でつくる材料で、刀鍛冶のために島根県の奥出雲で復興されました。これも砂鉄を溶かすところからはじめ、三日三晩の徹夜作業というたいへんな仕事です。夏場には仕上げや刀剣彫刻の仕事などをするようにしています。研ぎは鍛冶研ぎといって、こちらでかたち、身幅や寸法をととのえてから、仕上げの研ぎに出す。鞘師、研ぎ師の作業でまた2か月か3か月かかります。
刀を打つことを鍛えるというように、鍛錬は刀づくりの重要なプロセスです。師匠を取り囲むようにして三人の弟子が鋼を打ちます。経験を積んでくると師匠の心がわかってくるのですが、呼吸を合わせるのが難しい。ここを打ってくれという場所とタイミングを察して打たなければいけません。真ん中を的確に打つのも難しいものです。経験をつんでくると、反作用を利用してリズミカルに打てるようになります。
師匠は、打ちながら鋼がよくしまっているか柔らかいかの感触を感じ、色を見て、そのときどきの鉄の状態を判断します。赤らんでいる鋼に水をかける水打ちでは、表面に酸化鉄のかたちでついている余分な夾雑物を、水蒸気爆発で飛ばしてやります。折り曲げたときに夾雑物が入り込まないようにするわけです。鍛錬では鏨(たがね)で鋼を折り曲げで何層にもしていくのですが、たとえば15回折り曲げると3万層以上になり、粘りが出て折れにくく曲りにくい状態になります。
日本刀は、硬さと丈夫さという相反する条件を満たさなくてはなりません。しっかり鍛えた比較的炭素含有量の多い皮鉄によって、炭素量が少なく柔らかい心鉄がくるまれています。水打ちではまた、水の弾き方で鉄の成分を判断しています。鍛錬が充分となったら心鉄を皮鉄でくるみ、伸ばしていく。わずかでもねじれたら失敗です。寸法をはかりながら一日二日をかけて、ひとりで作業をすすめていきます。
心の状態を反映する
焼き入れ
とくに身が引き締まるのが焼き入れの工程です。そのときの自分の心の状態が反映されるので、朝から気持ちを整える。早朝、あたりがざわつかないうちに弟子と二人で部屋に入ります。部屋を暗くしておいて、刀と炎の色を見ます。刀全体の温度が元から先まで、むらのないようにする。気をぬくと冷めた部分ができるので、油断できません。鍛錬でも焼き入れでも、ふいごを加減しながら炎の色を調整しています。赤すぎてもいけません。いちばんいいところを見極める。刀身や炎の色味は、言葉ではなかなか表現できません。体験で覚えるしかない。
地鋼が全部ちがいますから、焼き入れの湯の温度も経験で決めなくてはなりません。一概には決められない。この鉄だったら少しゆるめにしておこうかという具合です。正宗の弟子が、湯の温度を盗もうとして湯に手を入れたところを腕を切り落とされるという逸話があるほど、大事なところです。反りのかたちもここで決まります。水は古い水、汲み置きして余計なガスが飛んだ落ち着いた水を使っています。
このとき表面につけた粘土の「はぜ」で焼きがうまく入っているかがわかります。水中で刀がそってくるので、土がはがれる。そのはがれ方が「はぜ」です。粘土は耐火性で鋼から外れにくいもの。産地は刀匠によってそれぞれ違いますが、私は父祖から伝わった大阪の土を使っています。
焼き入れの作業をいかに上手にしても、きちんと鍛錬していい鋼にしておかないと焼きが反応してくれない。なまくらの鋼で温度を高めてやっても、思うような焼きは入りません。焼きがさえない、明るい焼きが入っていない、いまひとつだということもある。刀匠の仕事にはいろいろ難しいプロセスがありますが、焼き入れがうまく一段落するときが、ほっとする瞬間です。
鍛錬と焼き入れは特に重要なポイントですが、もちろん研ぎに出したあとも、最後の最後まで気を抜けません。

月山伝の大きな特徴である、柾目が大きく波を打ったような綾杉肌の地肌

小槌

鍛錬中の月山氏。火花や鋼の色はもちろん、手に伝わる振動などで、鋼に含まれる炭素のバランスを判断する。鎚を打つ「向こう鎚」にも技量が要求される。

焼き入れでは、刀身に冷却速度を高めるため焼刃土(やきばつち)が塗られる。また、焼き入れ後の土の「はぜ」具合で仕上がり状態を判断する。
先達から
伝えられたこと
仕事場を綺麗にしておくのは鉄則。師匠であった父からの教えでもあります。とにかく清浄にしておく。神聖な場所でもあり、事故を防ぐという目的もあります。また刀匠は、つねに炎に向っていく。火傷を怖がっていたら仕事はできません。奥が深く若いころはえらい仕事についてしまったと思いました。
日本刀の本質は、切れるかどうかというのとはまた違うところにあります。研ぎ方によって切れるようにもなるし、居合いの先生が切れば切れる。われわれは、切れる以上のところを目指さなくてはいけません。また文化庁の決まりで、無銘では刀を世に出せません。自分の名前を彫る。何百年も残るので、それだけ自分の仕事に責任も感じます。私の師匠は、人間国宝になってから、世に出す作品が非常に少なくなった。自分で納得いかないと発表しない。それだけの責任を感じていたわけです。
師匠はあまりものを言わなかった人で、私はその仕事を見て覚えました。無言の指導です。曾祖父の初代貞一は、皇室の仕事をした名人と呼ばれた人ですが、その曾祖父も、刀匠は一生修行だという言葉を残しています。
後継者と日本刀の
魅力
明治維新では廃刀令が発布され、戦後は進駐軍によって製造が禁止されるなど、近代は苦難の時代が続きましたが、最近は各地で若手が育っています。中学生や高校生のとき、博物館かどこかで名刀を見て、自分もつくりたいと思うようになるようです。日本刀の凄さは、なかなかわかりにくいのですが、うちに来る若者は、月山独得の綾杉肌に惹かれている人が多い。刀鍛冶の後継者はひとまず心配ありません。むしろ山子(炭焼き)の後継者の方が心配です。一振りの刀をつくるのに12キロの炭俵を10俵使います。岩手産の特別の松炭です。日本刀の伝統を伝えるには、よい炭のつくり手が不可欠なのです。
刀匠の修行は文化庁の承認が必要であり、5年がひとまずの目処となります。8年で独立、注文に応えるには10年はかかる。実はそのあとが大変なのです。昔は子どものころに雑用からはじめたので、独り立ちまでもっと時間がかかったといいます。
刀剣は陶磁器や漆器などのほかの美術工芸品と比べて、日常生活では触れる機会が少ないものですが、本物を見て惹かれる人が多い。最近は海外からの注文も増え、日本の精神文化の象徴となっています。かえって日本人が、日本刀の魅力を忘れているのではないでしょうか。もちろん海外にも刀剣はありますが、根本的に違う。研ぎひとつとっても、これだけ多くのプロセスを経て光沢を出しているのは日本刀だけでしょう。海外の刀は戦のための消耗品がほとんどであり、美術的価値があるものでも、刀身そのものよりも、周辺の装飾に価値がおかれています。
反りも日本刀の特徴ですが、海外にも多少の反りがあるものはあります。逆に日本では権威の象徴となっているものは、平安以前では聖徳太子が持っているような直刀でした。平安以降に、しだいに反りができていった。両刃のものは普通にこしらえると直刀になります。片刃のものを直刀に仕上げるのは、これはまた難しいものです。科学技術である程度は解明・分析されても、再現できないところはいつまでも残ります。冶金学で分析した通りやっても名刀はできません。炭素や粘土の成分、温度や打つ回数をいくら解析しても、正宗はできないのです。やはり刀鍛冶としての体験を積み重ねたことでしか、わからないことがあるのだと思います。
どんな時代になっても、これだけは守り続けていかなくてはならないもののひとつが、刀匠の技術だと思います。日本刀は日本人の魂で、世界に誇る文化遺産です。