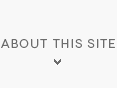機械に勘はわからない
日本酒ならではの
製造プロセス
日本酒とワインとビールは、同じ醸造酒ですが、製造工程はかなり異なっています。いずれにも原料の糖化とアルコール発酵という大きく分けて二つのプロセスがありますが、ワインでは糖分が最初からブドウにあるため、ブドウをつぶして酵母を加えればいいし、ブドウの皮に酵母がついていればそれで発酵する。アルコール度数が低いので1週間から10日でできるものもある。あとは熟成です。ビールは、麦芽自体が麹のようなもので、麦芽を糖化させて最初に甘い麦汁をつくっておいてから、酵母を加えます。日本酒では、米の澱粉を糖化させるところがまず難しい。麹をつくらなくてはならない。発酵中のタンクの中では、糖化されていない澱粉と酵母がいっしょに存在している。糖化が進むうちに、酵母の数も徐々に増えるのですが、糖化とアルコール発酵のバランス、つまり微生物の活動をコントロールしなくてはなりません。
あらためて日本酒の製造工程を概観してみると、まずは精米からはじまります。玄米のうち普通酒で30%、大吟醸になると半分を糠にして使わない。しかも大吟醸ではさらにその半分のうちの約40%が酒粕として酒にはならない。かなり贅沢な使い方をしているわけです。精米では摩擦熱によって水分が蒸発しますが、これを元に戻す。これを調湿、または枯らしといいます。摩擦熱が放散しきって完全に米が落ち着くまで、通常2週間から3週間はかかります。
うちの工場では、ここからが最初の工程。洗米、浸漬、蒸しを経て麹造りに入ります。浸漬は米を水に漬けることですが、単純なようでいて、百点満点の浸漬はまずありえません。どこかに多少のムラができる。同じ品種でも原料の状態は毎年変わるので、その年の米の癖をとらえて、米の漬け時間を考える。さらに、どういう麹にするかということを判断する。機械には癖はわかりません。成分分析でもすべてがわかるわけではない。夏の暑い年は澱粉の性質が変わって米が溶けにくい。それを頭に入れて浸漬を長くする。種麹の量も若干増やして、蒸米が硬くならないうちに麹室への引込みを終わらせてしまう。それは全部人間が主導していく。
麹造りでは、蒸した米を30度くらいまで冷まして、われわれがモヤシと呼んでいる種麹菌の胞子をふりかけます。まず一晩、引き込み床で寝かせてやると、夜の間に麹菌が芽を出し、発熱して蒸米が締まってくる。翌朝、3度から4度、品温が上昇しています。次に盛り棚に移します。そこでまた一晩面倒をみて、麹を誘導してやる。酒造りに適切な麹は、米の中に麹菌の菌糸が入り込んで、膨らんだような状態になっているもの。噛んで甘味があって、破精(はぜ)込み、つまり麹の菌糸がいい具合に米の中に入り込んでいるかを見ます。機械で麹をつくる場合も、ここまでは人間の感覚で判断します。吟醸麹の場合は、より長く破精込ませる時間をとる。菌糸をより深く入らせ、綺麗な酒をつくるために麹菌の菌体量を減らすわけです。麹菌は水分を求めて根をはやすのですが、外側を乾かしておいて、中の方に入りこんでくるようにするには、菌体量を少なくします。その分時間がかかるのです。
次が酒母造りです。糖をアルコールに変える酵母を増やす工程です。酛(もと)ともいいます。本仕込の前に、あらかじめ小さな仕込をして、酵母を大量に純粋に育てます。ここでも麹が必要なので酒母用の麹を用意しておき、酒母立てをします。大きな仕込では高温糖化酛、小ロットの場合は速醸酛という方式を使います。高温糖化酛の場合、60度くらいの高温で酛立てを行う。先にお米を溶かしておき、22、3度以下まで冷まして酵母を添加する。最初の段階で6時間で糖化させてしまうので、時間の短縮になります。タンクの中や器具類を殺菌する意味もある。安全に短時間で酛(酒母)をつくる近代的な酒母のつくり方です。速醸酛も明治時代に考案された技術ですが、低温で糖化を数日かけて行ないます。糖化と酵母の増え方のバランスをとりながら、少しずつ温度を調整する。糖化が終わると酵母が沸いてくる。速醸酛の方がどちらかというと複雑な味になります。
酒母造りでは、かつては家付き(蔵付き)酵母が主流でしたが、現在は少なくなっています。どんな酒になるかは博打のようなものですし、雑菌が入る可能性もある。酒造りは、結局優良酵母と雑菌との数の争いです。酵母を育てやすいのは、ある程度の酸がある環境。他の雑菌は酸があると生きていけない。速醸酛や高温糖化酛は乳酸を添加して酒母をつくり、家付き酵母を使う生酛系では、乳酸を添加せずに乳酸発酵させる。微生物同士の淘汰があって乳酸菌が乳酸発酵するので、他の雑菌が死滅する。そこに家付き酵母が入って、最後は酵母が勝つというわけです。そう考えると、日本酒はたまたまできた偶然の産物としか思えない。さまざまな条件が重なってできたもの。そのような条件を再現するのが、日本酒造りです。
酒母が完成すると、仕込の当日に仕込桶に移動し、仕込水と麹を投入して、麹から酵素を抽出する水麹というプロセスを経て、蒸米を投入します。最初が添仕込、次の日は踊りといって一日仕込を休み、仲仕込、留仕込となる。四日かけて仕込を行ないます。
一度に米と水を投入すると、酵母が薄まってしまい、雑菌に侵されやすい。だから添仕込で総米の6分の1。踊りでは、その時間だけ酵母が沸いてくる。仲仕込で添の倍、留仕込では添の3から4倍を投入する。うちでは普通酒で17日前後で発酵を終えますが、吟醸酒・大吟醸酒では、24日とか30日という長い発酵期間をとることになります。その後は醪(もろみ)から生酒(なまざけ)を搾る上槽、濁りを取り除く滓(おり)引き、濾過、殺菌処理を施す火入れと続きます。
先輩杜氏の教え
仕込は低温で発酵させるので留の段階で8度くらいが目標。添は踊りで酵母を沸かす必要があるので12、3度。高精白の純米大吟醸では留で6度くらいが目標です。何度で留めるか、どれだけ米を冷ますか、いずれも勘です。麹をつくるときも、手で触って判断します。麹造りの最初の段階である引き込みでは、機械制御の場合、温度計を見ますが、そこまでのプロセスで米を握って、勘で引き込み床で何度にするかを決めます。外気が冷え込むときには、そのあたりも勘案する。小さな仕込では条件がもっと厳しい。麻布の上で米をさわりながら温度をみて、号令をかけて室まで運ぶ。そこで蒸米の温度が均一になるのを待って種麹を振るわけです。私が初心者の頃に、先輩の杜氏が、34度とか5度を目標に引き込むと言っているのを聞き、温度計を米に挿したら、「そんな恥ずかしいことするな。手で充分や」と怒られました。
杜氏の仕事は、酒造りを統括することです。その下に頭、麹屋、酛屋の三役をはじめ、役がいろいろある。この集団をまとめて蔵人と呼びます。ただし蔵によって杜氏の役割も違う。麹もやって酒母もやって何でもやる杜氏もいれば、どんと坐って、麹造りは麹担当にまかせて、指示を出していく人もいる。杜氏にはまた、蔵人のまとめ役という意味もあります。

蒸した米に麹菌を繁殖させて米麹をつくる。麹の出来具合いの確認には、視覚、触覚、嗅覚が総動員される。

鏡開きなどでおなじみの菰樽(こもだる)。運搬時の樽の破損を防ぐために菰を巻いたことがはじまり。
私は社員で工場長という役職ですが、実際には杜氏の役割も担っています。新人の蔵人から杜氏になるまでの期間は人それぞれです。5年で杜氏になれる人もいれば、10年以上かかる場合もある。人から認められてはじめて杜氏。私はまだまだ、杜氏というのはおこがましい。かつては杜氏がやっていた小仕込は、いまは私たちが手造りでもやっています。機械造りでも、やっているうちに結局は人間がつくっているのだということを実感しました。つまるところ物量が多いかどうかの違いです。酒造りは、米を水に漬けるところからはじまりますが、そこから非常に気をつかいます。目を離せない。とにかく目で見て、手をかけてやる。それは今後、技術が進歩しても変わらないでしょう。
酒造りの技術以外のところでも、先輩杜氏にはいろいろ教えられました。いい酒をつくろうと思ったら人の和を大切にしろ、半年間同じ集団で酒をつくっていかなければならないので、悪口は絶対駄目だといわれました。
杜氏も蔵人も、感覚が優れているだけでなく、手先が器用でした。道具も自分で使うものは自分でつくっていました。たとえばタンクに蒸米を投入する時に使う籠というものを、頭の中で考えて設計図なしでつくってしまう。私が知っている頭も手先が器用で、複雑な配管の故障を簡単になおしてしまっていた。昔ながらの人でも、見事に機械に順応していたわけです。そういう人は機械でつくろうが、昔ながらの道具でつくろうが、いい麹をつくりますし、仕込の温度を留めるのも上手です。そういうところは、まだまだ追いつけません。酒造りに必要な基本的な生物学や化学についても、感覚的にわかっている。私たちが学校で習ってきたものをちゃんと身につけている。経験をベースにして勉強もしている。
失敗が勘を磨く
経験がないとまた勘も働かない。失敗も積み重ねて、ある程度極端なこともやってみないと、どこまでがやりすぎかどうかもわからない。先輩を見て、ここはもっとこうした方がいいんじゃないかと思ってやってみて失敗すると、先輩がやっていたことの意味がわかる。うまくいって改良できることもある。試行錯誤を繰り返して何が成功かを見つけていく。勘のいい人はすぐに正解を出せるのでしょうが、そういう人はきわめて少ない。
麹造りでは、手の感覚で温度だけではなく硬さをみている。中まで蒸せているか、芯が残ってないか、割れがないか、粘りがないか……とくに麹造りでは粘りのある米は失格です。粘りがあるのは水分が外側にあるということで、麹がまわりに破精て(菌糸を張って)しまう。だからといって水を吸わせればいいというわけではなく、加減をしてやらなくてはいけない。そのあたりはやはり勘です。米の状態をみるのは分析ではない。さわった瞬間にいいか悪いかを判断しています。

洗米や仕込に使われる水の性質は、酒の味を左右する重要な要素。

仕込んだ醪(もろみ)を木製のかくはん棒で混ぜ、醗酵を助ける。
大仕込の場合、機械から連続して蒸米が出てくるとき、最初と最後で感触が変わってくる。どこをとるかです。機械化されているとはいえ、大きな仕込の難しいところです。上の10%、下の10%は捨てて、真ん中の80%でいい蒸米が出るような浸漬をする。そこは勝負です。ロットの大小にかかわらず、与えられた環境でいい酒が生まれる環境を整えて、面倒をみてやるのがわれわれの使命です。
感覚を研ぎすませ、勘を働かせるためにも、健康には気をつけています。風邪はぜったいにひけない。酒造りの責任者は正月も休まないのが当たり前。麹の工程や小仕込の場合は、ほとんど泊まり込みです。
納豆のような発酵食品を食べないのも、昔からの決まり。つくりが大きい場合は影響はないのかもしれませんが、平行して小仕込もやっているので、そんなところにも気をつけています。